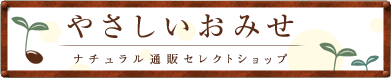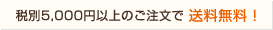Cherin チェリン 金【Sotto/ソット】について
故人を思いながら鳴らすおりんの音色は目を閉じ、手を合わせる間、美しく尊く心に染み渡ります。
さくらんぼのような形が愛らしい「Cherin(チェリン)」は、コンパクトで場所を取りませんし、佇まいはまるでオブジェのよう。上部の穴にりん棒を立てておさめるようになっていますが、叩いた後すぐにりん棒を戻しても、音が鳴り止むことはありません。黒色の敷布の上に置くことで、より美しい音色を響かせることができます。



くらしに寄りそう祈りのかたち
森羅万象を尊び、神仏に手をあわせる。
故人を偲び、ご先祖を敬う。
私たち日本人が古来から大切にしてきた「祈り」の心は、時代を経ても、脈々と受け継がれてきました。
しかし、その「祈り」を捧げる場においては、家族構成や住環境が変わってきた今、少しずつ変化が求められているようです。
『Sotto』は、現代の暮らしにそっと寄りそう祈りの道具です。
高岡銅器ならではの重厚さはそのままに、光沢感を抑えた金属の質感に自然木のぬくもりを合わせて和室にも洋室にも合うシンプルなデザインに仕上げています。
たとえば、家族が集うリビングスペースに。
あるいは、ベッドルームの傍のチェストにしつらえても。
仏壇や祭壇を置くスペースがない和室にも馴染み、さりげなくインテリアの中に溶け込みます。
『Sotto』は、あなたの祈りの心を大切に、ささやかな祈りの“場”を作るお手伝いをします。

おりんを鳴らす
本体のおりんの小さな隙間の少し上をりん棒で軽くたたくと、伸びやかな音色が響きます。
本体上部に収まっているりん棒は、叩いた後に元の場所に戻しても音が鳴り止むことはありません。さらに付属の黒い敷布をCherinの下に敷くことで、より音が伸びるようになります。

成熟の音
故人の思い出とともに、金属の熟成に合わせ音色もまた、経年とともにゆっくりと深みを増していくおりんです。
祈りを特別なものではなく、リビングや寝室に“そっと”しつらえて、生前と同じように、家族との団欒の中やパートナーとの語らいで話しかけるように、心を楽に鳴らしてみてください。

新たなものづくりへの真摯な挑戦で、暮らしに合わせた想いの道具を提案する 瀬尾製作所
国の伝統的工芸品「高岡銅器」に代表される銅製品の一大産地・富山県高岡市。約400年前、この地に高岡城を築いた加賀前田家二代当主・前田利長公が7人の鋳物師を呼び寄せたのが始まりです。
当初の鉄鋳物から、やがて、美術銅器や花器、仏具、銅像などが盛んにつくられるようになり発展。瀬尾製作所はこの歴史ある産地で、1935年の創業から一貫して仏具に関わる製品を手がけてきたメーカーです。
得意とするプレス板金の技術と、ものづくりへの真摯な挑戦を礎に、最近では住環境や暮らしの変化に合わせた、新しい仏具を独自に開発。オリジナルブランドSottoシリーズでは、現代のライフスタイルに合った、想いの道具や祈りの場づくりを提案しています。

Product story
Sottoシリーズで最初に生まれたプロダクトが「Cherin」でした。従来の仏具の常識を変える、現代の住環境に合った新しいブランドづくりへの挑戦は2010年にスタート。真鍮を丸くした形は、単に美しさや可愛らしさだけを追求してできたものではなく、ほかにはない、瀬尾製作所だからこそ可能な、長年のおりんづくりや、鍛造、板金加工で培った技術と、ものづくりへの情熱が可能にした形です。
音の美しさを追求するために中は空洞に。上下の間には隙間があり、金属同士はつながっていません。地面との接点はできるだけ小さく、敷物によって響きが良くなるよう工夫されています。りん棒の先端には、音が美しく鳴る水目桜の木を用いています。
開発者たちがそれぞれに最善を尽くし、約2年の歳月をかけてこの形にたどり着き、特許も取得しています。簡単にはできないからこそ実現したかった、日常の中で違和感なく溶け込む「Cherin」。ときを経ても変わらず進化を続けながら、多くの方に愛されている祈りの道具です。

Cherin(チェリン)カラーバリエーション
スタッフの声
- どんなインテリアにも違和感なく馴染む、かわいい「おりん」。小ぶりで場所を取らないので、コンパクトなスペースに置いて手を合わせることができます。澄んだ音色で、卓上ベルとしても使えます。
- やさしいおみせスタッフ ヤマシタ
商品詳細
仏具 おりん
| 名称 | Cherin |
|---|
| サイズ | φ55×H129mm(りん棒を含む) |
|---|
| 内容物 | おりん本体、りん棒、敷布、取扱説明書 |
|---|
| 材料 | 真鍮、天然木(りん棒の先端木部:さくら) |
|---|
| メーカー | 瀬尾製作所 |
|---|
| ブランド | ソット/Sotto |
|---|
| 原産国 | 日本製 |
|---|
| 備考 | 意商匠登録第1382910号、商標登録第5401108号 |
|---|
| お手入れの方法 | ・汚れ及びホコリが付着したまま強くこすると細かい傷がつく恐れがあるので、優しく布で拭き取るようにしてください。
・シンナーなどの有機溶剤及び薬剤が含まれた布等で拭かないでください。塗装の剥がれや変色する恐れがあります。 |
|---|